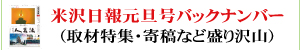|
川西町立大塚小児童へ「防災につながる科学」の理科特別授業
長年培ってきた地質調査の知見を活かし、地域の小学校で理科授業の一環として「防災につながる科学」を伝える取り組みを行っている応用地質株式会社(東京都千代田区)は、10月28日午前、川西町立大塚小学校で5年生と6年生の児童を対象に理科特別授業を行いました。同町での授業は小松小学校、犬川小学校に続いて3回目となります。
令和4年8月、山形県置賜地方は豪雨災害に見舞われ、JR東日本の米坂線が寸断されたほか、国道121号線の米沢ー喜多方間の道路法面が崩落、飯豊町では河川の氾濫により自動車が川に流されて運転していた人が行方不明となるなど、大きな被害が発生しました。この災害は、同社として置賜地方で「企業として何ができるか」、自然災害のリスクを「自分ごと」として捉える教育の必要性を強く感じ、企業の社会的責任を果たし、安心・安全な暮らしを支えていきたいと改めて考える機会となったとしています。
同日の理科特別授業は、同社東北事務所山形営業所所長で防災士の資格を有し、川西町犬川地区に住まいを構え、実際に被災を経験した人である貝羽哲郎さんが講師となり、6年生12名、5年生13名が授業を受けました。
6年生の授業では、「大地のつくりと変化」をテーマに、地球の仕組みを知ることを目的に、地球の大陸や高い山がどのようにできたか、大塚小学校周辺の地形を学びながら、活断層と地震時に揺れやすい場所などを考えました。砂と水を入れた円柱の透明容器にボールを入れて、激しく振った時にどのようになるか観察しました。地すべり模型実験では、山の斜面に水をまいた時に山が崩れる様子を知りました。またハザードマップの見方を確認するなど、防災への知識が深まる内容でした。
続いて5年生の授業では、「流れる水のはたらき」を学びました。川西町玉庭をスタートして、同町を南北に流れる犬川の上流から下流までの川幅や石の大きさを見ながら、なぜそうなるのかを考えたり、70年前と現在の地図を比べて、河川の変化を確認し洪水を防ぐ対策を学びました。
児童たちは、実験などを通して、自然の力を学びながら、生活の中での防災の知識を得ていました。